2022年09月25日
2022年09月20日
2022年08月18日
(20代女性)私は努力できないことに12年間悩んでいます【HappyScienceスピリチュアル人生相談 第32回】
(20代女性)私は努力できないことに12年間悩んでいます【HappyScienceスピリチュアル人生相談 第32回】
2012年11月20日
オリンピックの選手であろうと・・

Padmanaba01
仕事ができるようになるためには、
自己鍛錬が欠かせません。
たとえオリンピックの選手であろうと、
生まれつきの運動神経や体格などの
要素もあるでしょうが、
練習もせずに優れた記録を
出せたわけではないことは
間違いないことです。
これは英語などの
外国語を学ぶ場合でも同じです。
どれほど頭のよい人であっても、
勉強しなければ、
外国語ができるようには
絶対になりません。
一方、
勉強しさえすれば、
人によってマスターする速度に差はあっても、
できるようになるのです。
何であろうと、
鍛錬すれば、
その人に許された能力の範囲内で、
現在持っている以上の
実力になります。
頭脳にかかわることであろうと、
肉体にかかわることであろうと、
心にかかわることであろうと、
あるいは
宗教的な悟りにかかわることであろうと、
自分自身との戦いにおいて、
自己鍛錬によって
発展しないものなど、
まずないのです。
『幸福の法』
第二章 ワンポイントアップの仕事術
P90より


2012年11月19日
次のドアがひらく・・

MikeBehnken
現代では、
多くの人がサラリーマンとなりますが、
希望どうりの仕事であろうと
なかろうと、
結果的に
自分が勤めることになった
会社に対しては、
「自分はこの会社に縁がある。自分は天命を得たのだ」
と思うことです。
「自分はこの会社に縁があって入ったのだ。ここに天命があるのだ」
と思って働いた人は、
その会社で、
めきめきと出世し、
成功を収め、
自分の思うような仕事ができ、
結果的に天命そのものに
生きているようになるのです。
ところが、
「自分はこの会社に入るべきではなかった。何かの間違いであった」
と不平不満を言い、
給料のためだけに、嫌々仕事をしてる人が、
その会社で成功し、
出世することはありません。
たとえ、
その会社に天命がなくても、
一生懸命に努力した者には、
次の道が開けます。
努力しない者に、
次のドアが開くことはありません。
「どのような職場であっても、そこで最善を尽くして生きていくなかにこそ、天命は出てくるのだ」
ということです。
『幸福の法』
第二章 ワンポイントアップの仕事術
P85より


2012年11月18日
給料だけは上がることが・・

✿ nicolas_gent ✿
仕事が
できるようになる人と
ならない人を、
リトマス試験紙で調べるように、
簡単に見分ける指標があります。
それは、
「仕事に生きがいを持っているかどうか」
ということです。
仕事に生きがい感じてない人が、
仕事がよくできるようになることは、
まれなのです。
なかには、
生まれつき能力が高く、
「この仕事は嫌いだが、やれば、よくできる」
という人も、
いないわけではありません。
しかし、
嫌いな仕事は
長くは続かないものです。
それから、
いわゆる腰かけ的な発想で
勤めている人は、
仕事ができるようにはなりません。
「仕事ができるようになろうとは思わないけれども、毎年、給料だけは上がって欲しい。
仕事ができなくても、給料だけは上がることが、いちばん幸福である」
などと考えている人は、
仕事ができるようになる見込みは、
ほとんどないと言ってよいでしょう。
「仕事に生きがいを感じる」
ということは、
「自分がこの世に生を享けたことの意味を、職業を通して世の中に発揮できる」
ということです。
「自分はこの仕事を通して世の中に貢献している」
という気持ちが大事なのです。
それは「使命感」
と言ってもよいでしょう。
仕事に使命感を持っている人と、
持っていない人には、
非常に大きな違いがあります。
『幸福の法』
第二章 ワンポイントアップの仕事術
P82より


2012年11月17日
そこから逃れる方法は・・

broo_am
私は長年、宗教家として
経験を積んできたものとして
「人生に運命があるかどうか」
と訊かれたら、
「あるでしょう」
と答えます。
ただ、その「あるでしょう」
という答えは、
「決まった筋書きがある」
という意味ではありません。
「人には、それぞれ魂の傾向性というものがあるので、その傾向性を見れば、その人の人生は、だいたい予想がつく」
ということです。
その意味において、
やはり、「運命はある」
と言わざるをえないのです。
しかし、
その運命を乗り越える方法もあります。
自分の運命が、
もし悪しき運命、
避けたい運命であるならば、
そこから逃れる方法は一つです。
それは自分の
魂の傾向性をはっきりつかむことです。
すなわち、
研究心を持って、
自分を観察し、
他人を観察し、
その魂の癖や傾向性、
長所、短所を
緻密に分析しながら、
「自分を変えていこう。いまの自分を脱ぎ捨てていこう」
と思っている人は、
運命が変わっていくのです。
『幸福の法』
第一章 不幸であることをやめるには
P64より


2012年11月16日
失敗の多い人生を・・

The Knowles Gallery
人生には
悩みや苦しみが
たくさんあるでしょうが、
それは実際、
とてもありがたいことなのだと
思っていただきたいのです。
悩みがないということは、
また、
発展性もないことを意味します。
みなさんが持っている
悩みのなかには、
解決がつかないものも、
おそらくあるでしょうが、
実は、
そのなかに無限の発展の可能性が
宿されているのです。
失敗の多い人生を
悔やむ必要はありません。
失敗のなかには、
次の創造の芽、
発展の芽が、
必ず隠されているものです。
この自己認識の変容、
拡大、
発展こそが、
実は魂の成長なのです。
この自己認識の変化こそが、
実は魂としての成功であり、
それを得るために、
肉体を持って、
この世に生まれ、
赤ん坊から
何十年もかけて大きくなり、
年を取って死んでいくのです。
『幸福の法』
第一章 不幸であることをやめるには
P53より


2012年11月15日
他人がいなければ・・

brsun
人生の目的の一つは、
他者とのかかわりです。
「他者とのかかわりにおいて自己を知り、また、お互いに影響を与え合う存在として生きていくことを学ぶ」
ということです。
他人は自分の思うようにならないものですが、
いろいろな人がいるということは、
自分自身を教えてくれるという意味で、
ほんとうにありがたいことなのです。
「こんな人が存在するのか。こんな考え方があるのか。こんな性格がありうるのか。」
と、非常に不思議に思うこともありますが、
他の人から逆照射して
自分自身を知るためには、
多様な能力や個性を持った人が
どうしても必要なのです。
それで、
人間は共同生活をしているわけです。
他人がいなければ、
自分自身のことが
まったく分からないのです。
実は、これが、
仏や神といわれる存在が
世界を創った理由でもあります。
仏神は、
相対的な世界を展開することによって、
つまりお互いを
磨き合う世界を創ることによって、
自己認識を深め、
自己の可能性を楽しんでいるのです。
『幸福の法』
第一章 不幸であることをやめるには
P49より


2012年11月14日
一言で言えば“自己中”です・・

Anthony DeLorenzo
あの世には
地獄といわれる世界がありますが、
死後、この世界に行く人の特徴は
一言で言えば、
“自己中”です。
みな自己中心の考え方をしていて、
自分の立場を
一生懸命説明することには
非常に長けているのですが、
本当に相手の立場にたって、
その人の幸福を考えるということは、
非常に少ないのです。
「自分が犠牲になってでも、その人のために尽くそう」
と思うような人は、
この世界にはまず見当たりません。
また、
地獄にいる人の特徴は、
自ら反省するよりも、
仲間を増やそうとすることにあります。
自分と同じような境遇の人を増やし、
仲間を増やせば、
自分の苦しみが
薄れるような気がするのです。
たとえて言えば、
「自分だけが貧乏なのはつらいけれども、ほかの人も貧乏になれば、気持ちがすっきりする」
というような考え方です。
確かに、
「平等の思想」のなかには、
よいものも当然ありますが、
そのなかには、
もし「みなが不幸になれば、平等でよい」
という考えが入っていたならば、
それも一種の地獄的な考え方であるので、
気をつけなければいけません。
『死んでから困らない生き方』
第二章 地獄からの脱出
P96より


2012年11月13日
あなたが憎んでいる人にも・・

Nathan O'Nions
すべての人間には、
「幸福になる権利」
があるだけでなく、
「幸福になる義務」
があります。
そして、
幸福になる義務は、
自分だけにあるのではなく、
ほかの人にもあるのです。
あなたが憎んでいる人にも、
幸福になる権利と義務があるわけです。
一人一人が
幸福になることによって、
世の中がユートピアに変わっていきます。
自分にも他人にも、
幸福になる義務があり、
その義務をきちんと果たしたならば、
世の中は
ユートピアになるでしょう。
それでは、
その、幸福になる義務を果たすためには、
どうすればよいのでしょうか。
それは、
他者の存在を肯定することです。
いろいろな価値観や
生き方があり、
各人にそれぞれの長所、
よさがあります。
短所と見えるもののなかにも、
実は、その人の
優れた個性があるかもしれません。
「すべての人間が、神の子、仏の子として成長し、大きくなり、成熟していくことができるのだ。成熟することによって、自分自身の罪や他人の罪など、あらゆる罪を乗り越えていくことができ、困難と見えしものを乗り越えていくことができるのだ」
ということを
考えていただきたいのです。
『ストロング・マインド』
第三章 心の成熟について
P138より
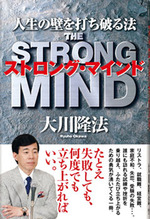

2012年11月12日
ご主人にたいしても・・

snowpeak
人はみな、
自分にとって
都合のよい価値観のみを
信奉したがる傾向を持っているので、
価値観の多様性を
認めるための努力が必要です。
人間には
いろいろな種類の人がいますし、
いろいろな考え方や
生き方がありますが、
「これがいけない、あれがいけない」
ということばかりを言う人がいます。
例えば、
時間に厳しくて、
とにかく時間が気になって
しかたがない母親であれば、
「子供が時間どおりに動かない」
ということが絶対に許せません。
それ以外の部分で、
いくら子供に良いところがあっても、
自分自身が
時間どおりにビシッと行動しないと
気が済まないタイプであるため
子供も時間どおりに動かないと、
絶対に許せないのです。
そういう人は、
ご主人に対しても、
同じように当てはめようとします。
一つのものの見方で、
すべてを見ようとし、
自分の生き方で、
ほかの人を裁こうとします。
しかし、
人を裁くのを少し待って、
「人間には違いがあり、世の中には、いろいろな人がいる」
ということを考えてみてほしいのです。
今の子供の例で言えば、
「確かに、時間に関しては、いいかげんなところがあるかもしれないが、この子には非常に人付き合いのよいところがある。この人付き合いのよさが、少し時間を破ったりすることにつながっているのだな」
という見方もあるでしょう。
そのように、
「多様なものの見方ができるようになり、いろいろな人間の長所を受け入れることができるようになる」
ということは、
実は、人間としての成長なのです。
『ストロング・マインド』
第三章 心の成熟について
P109より
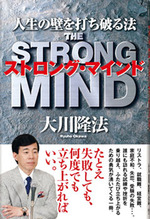

2012年11月10日
夜、寝るころになって・・

DKI Photography
人間は、
自分中心に
物事を考えているうちは、
なかなか幸福になれません。
「自分が傷ついたかどうか」
「自分が不幸かどうか」
ということを思っている間は、
実は幸福になれないのです。
幸福な人は、
自分のことを考えている時間が
短くなってきます。
真に幸福な人は、
一日中、自分のことなどは
まったく考えてません。
夜、寝るころになって、
ふと気がつくと、
「今日は、自分のことを考えなかったな。『私は』という主語で一度も考えなかったな」
と思う人は、
かなり幸福な人です。
「○○さんは、どうだったかな」
「あの人は、どうだったかな。うまくやれたかな」
などと、ほかの人を考え、
その人をよくしていこうと
考えている人は、
幸福な人なのです。
その反対に、
一日中、
自分のことを考えている人は、
不幸な人です。
『ストロング・マインド』
第三章 心の成熟について
P107より
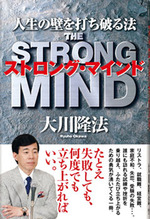

2012年11月09日
なんでも食べられる人は・・
2012年11月08日
ろくなことにならない・・

Nicolas_Goulet
日本では現在、
交通事故の年間の死者は
一万人を割るようになりました。
しかし一方では、
年に三万人もの人が
自殺しています。
この自殺者の数を
何とかして減らしたいと
私は考えています。
自殺について、
総じて言えることは、
次のようなことです。
自殺する人の主な原因は、
仕事の行き詰まり、
対人関係の問題、
病気、
借金などであり、
最後は、
「苦しみから逃れたい」
という衝動で死ぬ場合が多いのですが、
結局、あの世のことが
よく分かっていないから、
そういうことをするのです。
私がさまざまな機会に述べているように、
自殺者が天国に行くことは
極めてまれであって、
地獄、もしくは
地獄以前の段階にいることが多いのです。
自殺者のなかには、
自分が死んだことが分からずに、
地上の人と
同じように生活している人や、
地縛霊となって、
自分が死んだ場所に
漂っている人が数多くいます。
したがって、
「自殺すると、ろくなことにならない」
ということを、
生きているうちに、
知識として
しっかり頭に入れておくことが
大切なのです。
『幸福へのヒント』
第一章 お父さんの幸福へのヒント
P34より


2012年11月06日
ある意味で試されてます・・

死後の世界について、
「知らない」
「信じられない」
と言う人の考えは、
「もし、ほんとうにそのような世界があり、仏や神がいるのならば、それをこの世の人間に分かるようにしていなければ不親切ではないか。そういう存在があるのなら、もっと人間に分かるようにしているはずである。人間に分かるようなかたちになっていない以上、そういうものは存在しないのだ。実験して確かめることもできないのでは、信じるに値しない」
ということだと思います。
しかし、
誰もが分かるようになっていないことには
理由があるのです。
その理由とは、
「この世の世界そのもの、数十年の人生そのものが、ある意味で、一種の試験である」
ということです。
人間は、
本来の世界である
霊的世界から生まれてきて、
肉体に宿り、
物質世界のなかで生きています。
そして、
「この物質世界のなかで生きながら、どれだけ霊的な人生観を手に入れることができるか。かつて仏神から学んだ教えを、どれだけ実体験し、実践できるか」
といことを、
ある意味で試されています。
人間は人生において、
さまざまな経験を積んでいきますが、
それは試験でもあるのです。
『信仰のすすめ』
第2章 死後の世界について
P63より


2012年10月27日
蚊取り線香に・・

@dd_number
悪霊は、
その人の最も弱いところを
攻めてきます。
これが悪霊の特徴です。
その人の暗い部分、
えぐれている部分、
出っ張っている部分を
重点的に攻めてくるので、
そうした部分をつくらないことが
大事なのです。
その意味において、
反省は悪霊に対する
最大の防御でもあります。
防御する過程において
出す念いが、
悪霊たちの好まないものと
なっているからです。
蚊取り線香に
蚊が近寄りたがらないように、
反省をしている人に
悪霊は近寄りたがらないのです。
悪霊は蚊のようなものなので、
そうした蚊が飛びまわり、
血を吸おうとしているのを
発見したならば、
蚊取り線香の煙のように、
悪霊が最も嫌うものを
出すことが大事です。
悪霊がもっとも嫌うのは、
結局、正しい生き方です。
正しい生き方に戻るために
反省をするのです。
『不動心』
第五章 悪霊との対決
P171Pより

2012年10月26日
同じ苦しみを・・

Marc Veraart
悪霊は、
「とにかく人間を堕落させたい」
「自分たちと同じ苦しみを味わわせてやりたい」
という気持ちをもっています。
したがって、
彼らは向上心をもって
努力している人が
非常に苦手です。
もっとも、
向上心をもっているのに、
悪霊に惑わされている人もいます。
それは、
増上慢になりやすい人、
自己顕示欲をもっている人、
「自分が、自分が」
という気持ちの強い人などです。
そうした人を
悪霊は惑わすことができます。
しかし、
謙虚に自分自身を見つめながら、
前へ前へと
進んでいる人に対しては、
悪霊はなすすべがなく、
取りつく島がない
というのが現実です。
『不動心』
第五章 悪霊との対決
P169Pより

2012年10月25日
もっと高い身長に生んでくれ・・

dice-kt
悪霊との対決は、
「反省」をぬきにしては
語れないものがあります。
消極的な方法に見えますが、
反省は立派な対決方法なのです。
それは、
悪霊が憑いている人の
言動を見てみれば
よくわかります。
彼らに共通しているのは、
「自分には決して責任がない」
という言い方をすることです。
「制度が悪かった」
「会社が悪かった」
「あの人が自分を害した」
「こうした家庭に生まれたのが不運だった」
「田舎に生まれたのが間違いだった」
「家族や親戚が悪かった」
「親がもっと高い身長に生んでくれなかったのがいけなかった」
このように、
責任を外部に転嫁しようとするのが
悪霊の典型的な姿なので、
こうした傾向のある人は、
「自分は悪霊に憑かれているか、悪霊の候補生だ」
と思っていただきたいのです。
「不幸の原因を他に転嫁しようとする気持ちがあったとき、自分は悪霊の虜になっているのだ」
ということを
知らなくてはなりません。
こうしたときに大事なのが
反省なのです。
まず、
「他人との不調和が起きた原因は、他人だけではなく自分自身にもあったのではないか、自分自身にも何か問題があったのではないか」
と考えてみることです。
そして、
もし自分自身に
間違いがあったことを発見したならば、
その点を
相手に直接詫びるか、
あるいは
心のなかで詫びるのです。
さらには、
神に許しを乞い、
そうした過ちを
二度と犯すまいと思うことです。
『不動心』
第五章 悪霊との対決
P162より

2012年10月24日
かわいそうな自分・・

Daniel2005
人生の途上において
悲しい出来事や、
苦しい状況に
直面することもあるでしょう。
そのときに大切なのは、
流れていく時間のなかで、
自分を大切にしながら
力を蓄えていくことです。
もがき苦しみ、
おぼれてしまうのではなく、
自分を磨いていくのです。
その際に最も肝心なのは、
「神への信仰」
「神への愛」です。
悩みの渦中にあるときには、
「自分には神への愛があるだろうか」
ということを考えてみてください。
たいていの人は
自己愛の虜になっています。
「こんなにかわいそうな自分」
ということを一生懸命考え、
他人の同情を得たいと思うのに、
だれからも同情の声がないー
この点が問題なのです。
こうしたときには、
背筋を伸ばして、
大空を見上げてみてください。
悩みの渦中にある人、
悪霊の虜になっている人は、
たいてい、
しゃがみ込んで、
太陽に背を向け、
自分の小さな影ばかり
見つめているのです。
それではいつまでたっても
光は見えません。
すっくと立ち上がり、
太陽に向かって
大きく背伸びをすることです。
これが「神への愛」
ということなのです。
小さな自分ばかり見つめないで、
神のほうを振り返り、
感謝の気持ちを抱くことです。
「自分はいかに大きな愛を与えられているか」
「不幸なように見えても、時間の流れのなかでは、それはたいしたことではなく、むしろ大きな向上への糧となっているのではないだろうか」
と考えてみるのです。
どのような試練がきても
そこから教訓を
学んでいく姿勢さえ忘れなければ、
人間は立派になって
いくしかないのです。
『不動心』
第五章 悪霊との対決
P160より




